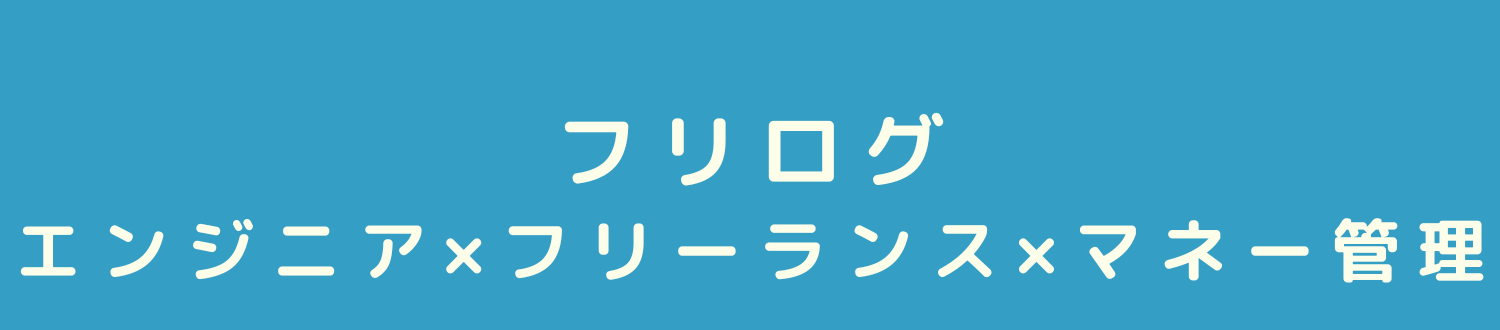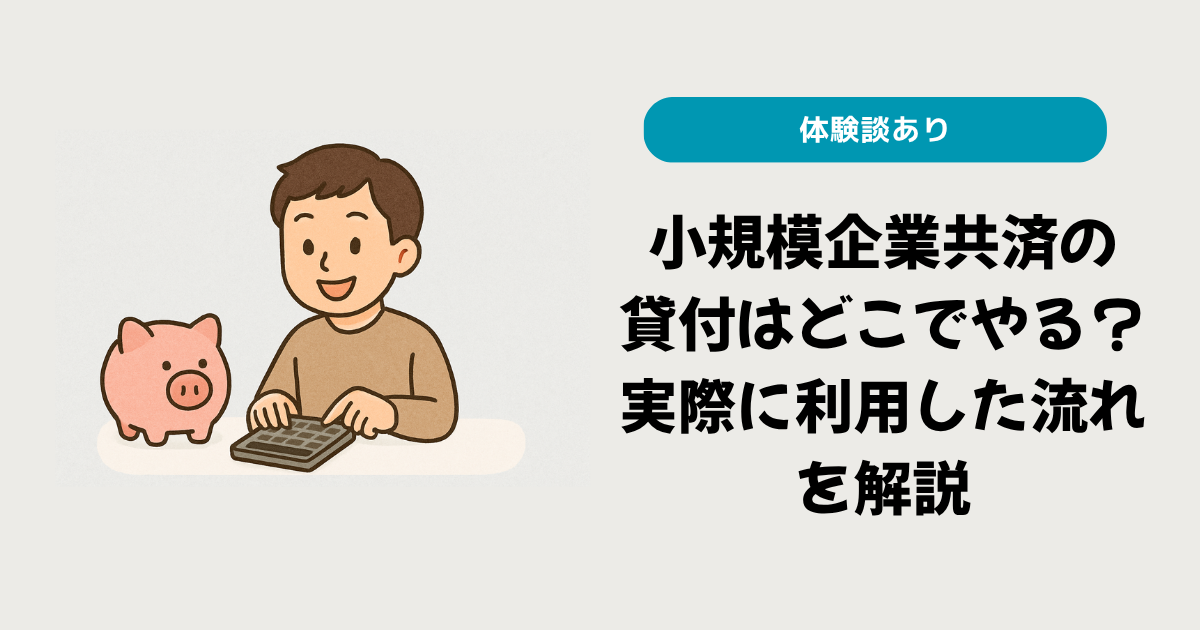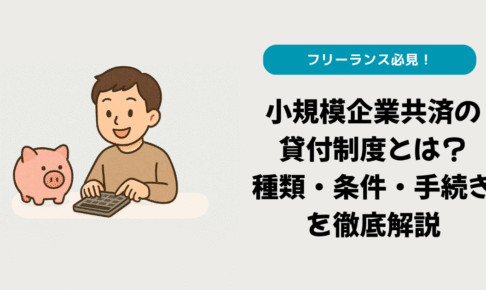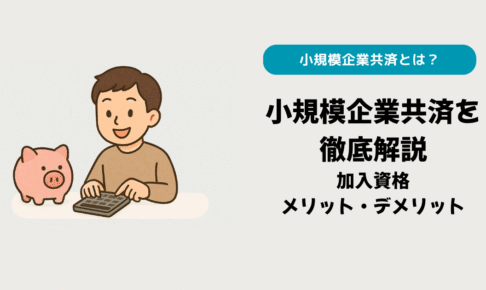- 小規模企業共済の貸付を利用してみたい
- どこで手続きしたらいい?窓口はどこ?
- 実際の手続きの流れを知りたい
小規模企業共済の貸付制度は、所得控除を受けながら資金調達ができる優れた制度です。
しかし、手続き方法が複雑で、初めて利用する方にとってはハードルが高いと感じるかもしれません。
この記事では、実際に小規模企業共済の貸付を利用した経験を基に、手続き窓口から具体的な流れまで詳しく解説します。
2022年12月から小規模企業共済に加入し、商工組合中央金庫(商工中金)の窓口で一般貸付を実際に利用した実体験を交えてお伝えします。
この記事を読むことで、小規模企業共済の貸付手続きの全体像が把握でき、効率的に資金調達ができるようになります。
必要な書類の準備方法や、窓口での手続きの流れ、失敗しないためのポイントまで、実践的な情報をお届けします。
小規模企業共済の貸付手続きについて、具体的で実用的な情報をお探しの方は、ぜひ最後までお読みください。
Contents
小規模企業共済の貸付制度とは
貸付の種類(一般貸付・特別貸付)
小規模企業共済の貸付制度には、大きく分けて2つの種類があります。
事業資金などを簡易かつ迅速に借りられる「一般貸付」(利率:年1.5%)と、特別な事情がある場合に貸付を受けられる「特別貸付」(利率:年0.9%)です。
特別貸付は特別な事情がある場合に利用できる貸付制度です。利率は年0.9%と一般貸付より低く設定されていますが、利用条件がより厳しくなっています。
一般貸付と特別貸付では、手続き窓口や必要書類、審査基準などが異なります。そのため、どちらの貸付を利用するかによって、手続きの流れも変わってきます。
利用を検討する際は、まずどちらの貸付に該当するかを確認することが重要です。
利率の違い
- 一般貸付 利率:年1.5%
- 特別貸付 利率:年0.9%
一般貸付の利率は年1.5%で、事業資金などの貸付を簡易迅速に受けられます。
特別貸付の利率は年0.9%と、一般貸付より低い利率で借りることが可能です。
ただし、特別貸付は特別な事情がある場合のみ利用できる制度となっています。
具体的には、災害や事業の継続に支障をきたす緊急事態が発生した場合などです。
小規模企業共済の貸付手続き窓口はどこ?
一般貸付の手続き窓口
借入窓口を登録している場合
借入窓口を指定の金融機関支店に登録することで、普段利用する銀行などで貸付を利用できるようになります。
商工組合中央金庫の本店または支店の場合
借入窓口が商工組合中央金庫の本店または支店の場合は、登録した窓口先にいきましょう。
午後2時までに窓口で手続きをすると、即日で貸付資金の受取が可能です。
ただし、窓口は12:00~13:00の間は休業となりますので注意しましょう。
その他の金融機関の場合
その他の金融機関の場合は、貸付の申込みから資金交付まで2~3日程度の日数を要す場合があるため、事前に登録金融機関に問い合わせするようにしましょう。
借入窓口を登録していない場合
借入窓口の登録をしていない場合、商工組合中央金庫の本店または支店での手続きになります。
商工組合中央金庫の本店または支店では、午後2時までに窓口で手続きをすると、即日で貸付資金の受取が可能です。
ただし、窓口は12:00~13:00の間は休業となります。
特別貸付の手続き窓口
商工組合中央金庫での手続き
特別貸付の窓口は、商工組合中央金庫の本店または支店での手続きになります。
一般貸付とは異なり、特別貸付は借入窓口の登録ができません。
そのため、必ず商工中金の窓口に直接足を運ぶ必要があります。
特別貸付の手続きでは、一般貸付よりも多くの書類が必要になります。
事業計画書や資金使途の詳細な説明書など、事前に準備しておく書類が増えるため注意が必要です。
特別貸付は特別な事情がある場合の貸付制度であるため、手続き前に商工中金に相談して、利用可能かどうかを確認することをお勧めします。
窓口での手続き時間は、書類の内容確認なども含めて一般貸付よりも長くなる傾向があります。余裕を持って窓口を訪れるようにしましょう。
【体験談】実際に小規模企業共済の貸付を利用してみた
利用前の準備
・実印
・本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・保険証など)
・収入印紙(借入金額に応じた金額の印紙)
・契約者番号がわかる書類(貸付限度額のお知らせのハガキ・共済手帳など)
必要書類を用意することで、窓口での手続きがスムーズになります。
印鑑登録証明書は発行から3ヶ月以内の原本のみが有効である点に注意しましょう。事前に市役所で手続きしておくと良いです。
運転免許証や保険証などの本人確認書類は、記載されている情報が事実と異なる場合は借りられなくなる恐れがありますので、事前に確認しておくことが良いです。
必要な収入印紙の金額<
手続きには、収入印紙が必要です。
郵便局などで事前に購入しておきましょう。
| 借入金額 | 収入印紙の金額 |
|---|---|
| 10万円 | 200円 |
| 15万円〜50万円 | 400円 |
| 55万円〜100万円 | 1,000円 |
| 105万円〜500万円 | 2,000円 |
| 505万円〜1,000万円 | 1万円 |
| 1,005万円〜2,000万円 | 2万円 |
商工中金での手続きの流れ
僕が実際に一般貸付を商工組合中央金庫(商工中金)の窓口での手続きで利用した際の流れを解説します。
平日の昼間に窓口に行きましたが、所要時間30分程度で資金を受け取ることができました。
窓口の混雑度によっては1時間くらいかかる可能性もあると思います。
- 必要書類などの用意
- 商工中金の窓口に行く
- 必要書類を担当者に渡す
- 契約者情報や貸付内容などの手続き
- 手続き内容の確認(印紙貼付け・実印押印)
- 資金受取
窓口での受付
実際に商工中金の窓口で手続きをします。
窓口では「一般貸付を利用したい」ことを伝えましょう。
借入窓口が商工中金の場合は、午後2時までに窓口で手続きをすると、その日のうちに貸付けを受けることができます。
必要書類の提出
小規模企業共済の契約者確認のため、必要書類を担当者に渡します。
本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・保険証など)、契約者番号がわかる書類(貸付限度額のお知らせのハガキ・共済手帳など)、印鑑登録証明書を渡しました。
手続き内容の入力
・借入内容の入力(借入金額・借入期間・資金用途など)
契約者情報や貸付内容などの手続きをします。
タブレットでの手続きでしたが、担当者と確認しながら内容を入力しました。
僕の場合、今回の貸付額が30万円ほどでしたので、借入期間は6ヶ月または12ヶ月でした。
今後も借換を利用していく場合は、借入期間12ヶ月の方が良いです。
※借入の返済期日を過ぎると延滞利子が発生するため、6ヶ月の場合は期日ギリギリで返済や再度借換をしなければいけなくなり、スケジュールに支障をきたす場合があります。
印紙貼付け・実印押印
最終的な手続き内容の確認で問題がなければ、用意した印紙の貼付けをし、書類に実印の押印をします。
あとは、窓口の方で資金が用意されるのを待つだけです。
資金受取
窓口での資金が用意され、受取をすれば手続き完了です。
受取金額に問題がないか、その場で確認しておきましょう。
小規模企業共済の貸付で失敗しないためのポイント
手続き時の注意点
借入期間の選び方
6ヶ月と12ヶ月から選択できますが、継続的に借換を利用する予定がある場合は12ヶ月を選ぶことをお勧めします。
6ヶ月の場合、返済期日が近づくと延滞利子が発生するリスクがあります。
期日ギリギリでの返済や借換が必要になり、スケジュール管理が難しくなる可能性があります。
必要書類の準備
本人確認書類、契約者番号がわかる書類、印鑑登録証明書は必ず持参してください。
書類が不足していると手続きが遅れる原因になります。
窓口の営業時間
商工中金の本店・支店は午後2時までに手続きを完了すれば即日貸付が可能です。
ただし、12:00~13:00は窓口休業時間のため注意が必要です。
よくある質問
Q1: 即日貸付は可能ですか?
一般貸付の場合、借入窓口を商工中金に登録していれば即日貸付が可能です。
ただし、午後2時までに窓口で手続きを完了する必要があります。
Q2: 借入窓口の変更はできますか?
はい、借入窓口の変更は可能です。
小規模企業共済の公式サイトから手続きできます。変更後は新しい窓口で貸付を利用できるようになります。
Q3: 返済方法はどうなっていますか?
返済資金(現金)を借入窓口に持参しましょう。
また、振込による返済を希望される場合は、振込返済の可否やお手続方法について、借入窓口(金融機関)へお問い合わせください。金融機関により、振込返済の取り扱いをしている場合があります。
出典:共済契約者貸付制度を利用した借入金の返済手続きの流れについて教えてください。s
Q4: 貸付限度額はどのように決まりますか?
貸付限度額は、小規模企業共済の掛金納付額に応じて決まります。
毎年送付される「掛金納付状況及び貸付限度額等のお知らせ」で確認できます。
こちらの記事で、貸付限度額の決まり方・自分でも算出できる方法を解説しています。
Q5: 特別貸付の審査は厳しいですか?
特別貸付は特別な事情がある場合の制度です。
事業計画書や資金使途の詳細な説明が必要で、審査は一般貸付よりも厳しくなります。
まとめ
小規模企業共済の貸付手続きのポイント
小規模企業共済の貸付制度を利用することで、所得控除を受けながら手元にお金を残すことができます。実際に利用した経験を基に、手続きの流れと注意点を詳しく解説しました。
特に重要なポイントは以下の通りです。
- 一般貸付(年1.5%)と特別貸付(年0.9%)の2種類があり、手続き窓口が異なる
- 一般貸付は借入窓口の登録が可能で、商工中金なら即日貸付が利用できる
- 特別貸付は商工中金の本店・支店でのみ手続き可能で、より多くの書類が必要になる
- 午後2時までに手続きを完了すれば即日で資金を受け取ることができる
- 印鑑登録証明書は発行後3ヶ月以内の原本が必要で、事前準備が重要
- 借入期間は12ヶ月を選ぶことで、継続的な借換利用時にスケジュール管理が楽になる
小規模企業共済の貸付制度は、フリーランスや個人事業主にとって非常に有用な制度です。適切な準備と手続きを踏むことで、効率的に資金調達ができるでしょう。