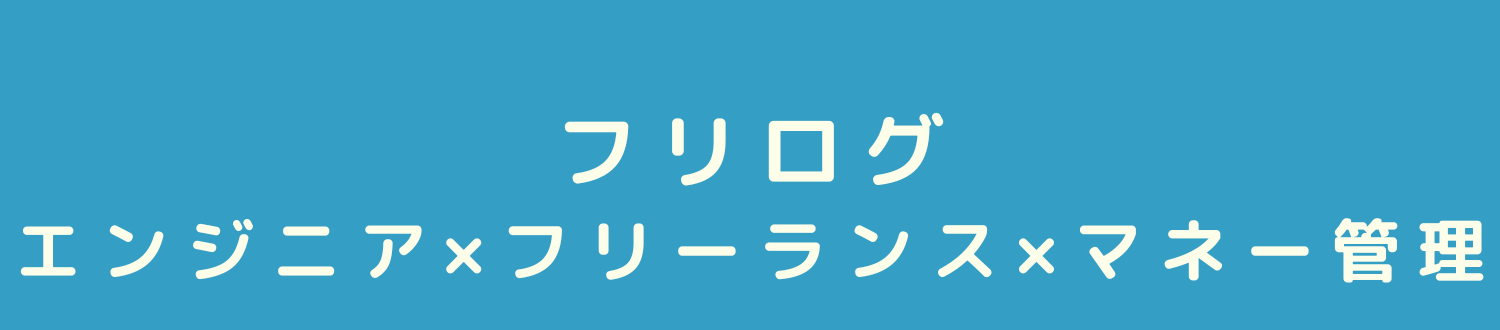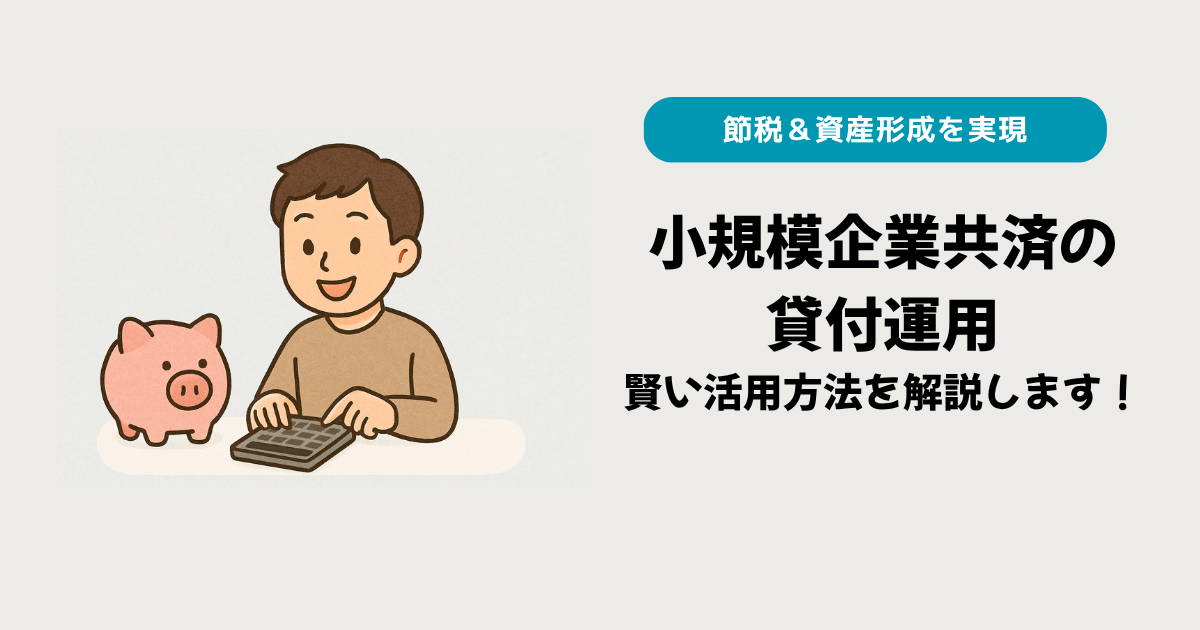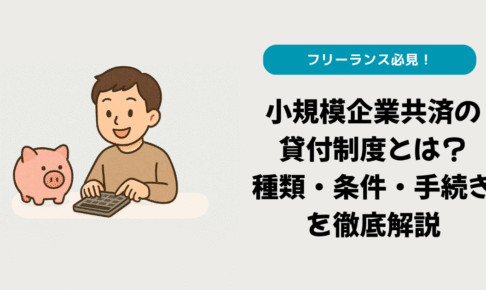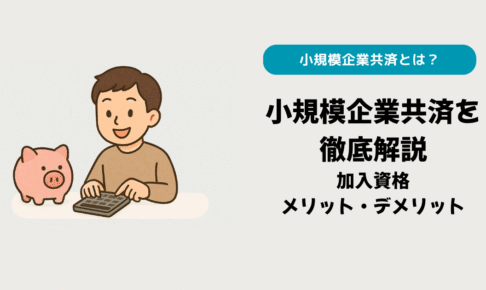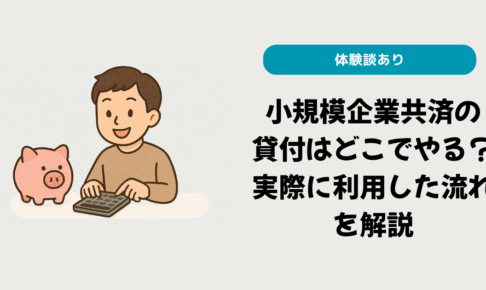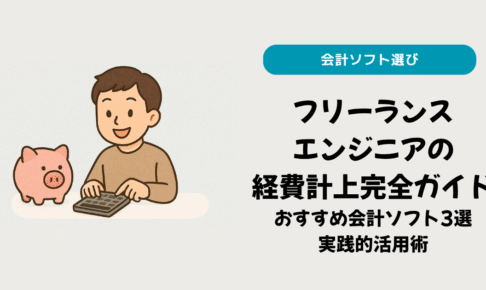- 小規模企業共済の貸付制度って本当にお得なの?
- 運用方法がよくわからない
- デメリットはないの?
事業資金の調達に悩むフリーランスや中小企業経営者にとって、小規模企業共済の貸付制度は魅力的な選択肢の一つです。
しかし、低金利というメリットだけに注目して安易に利用すると、思わぬ落とし穴にはまってしまう可能性があります。
本記事では、小規模企業共済の貸付制度について、基本的な仕組みから効果的な活用戦略まで、実際のフリーランスエンジニアとして小規模企業共済を活用している筆者の経験をもとに詳しく解説します。
Contents
小規模企業共済の貸付制度とは?
小規模企業共済の貸付制度の概要
小規模企業共済の貸付制度は、共済契約者が積み立てた掛金の中から、事業資金や生活資金などを借り入れできる制度です。
最大の特徴は、銀行融資と比較して低金利かつ迅速な資金調達が可能な点にあります。
貸付限度額は掛金納付月数に応じて決まり、掛金の7割から9割程度まで借り入れることができます。
金利は年0.9%から1.5%程度と非常に低く設定されており、民間金融機関の事業資金融資と比べて大幅にコストを抑えられます。
また、担保や保証人が不要で、審査期間も比較的短いため、急な資金需要にも対応しやすい制度となっています。
ただし、貸付を受けると将来受け取る共済金から元利金が差し引かれる点は注意が必要です。
貸付の種類と特徴
小規模企業共済の貸付制度には、大きく以下の2種類があります
- 一般貸付:事業資金全般(金利1.5%)
- 特別貸付:特定条件下で優遇金利(0.9%)
一般貸付では事業資金全般に利用でき、金利は年1.5%となっています。
特別貸付とは、特別な事情がある場合に限り認められる貸付制度で、一般貸付よりも低い利率で借りることができます。
ただし、利用にはそれぞれの条件を満たす必要があります。
- 緊急経営安定貸付
- 傷病災害時貸付
- 福祉対応貸付
- 創業転業時・新規事業展開等貸付
- 事業承継貸付
- 廃業準備貸付
例えば、「緊急経営安定貸付」は、経済環境の変化などによる一時的な売上減少により、資金繰りに著しく困難な場合に利用できる制度ですが、借入資格要件を満たす必要があります。
各貸付制度の詳細や手続きについては、以下の記事でも解説していますので、併せてご確認ください。
小規模企業共済の貸付制度のメリット・デメリット徹底比較
【メリット1】低金利で迅速な資金調達が可能
小規模企業共済の貸付制度最大のメリットは、年0.9%から1.5%という圧倒的な低金利で資金調達できる点です。民間金融機関の事業資金融資が年2%から5%程度であることを考えると、金利負担を大幅に軽減できます。
一般貸付の場合は、理由を問わず即日で借入が可能です。特に急な資金が必要になった場合などに対応しやすい制度といえます。
【メリット2】担保・保証人不要で手続きが簡単
小規模企業共済の貸付制度では、担保や保証人を用意する必要がありません。
自身で積み立てた掛金そのものが担保の役割を果たすため、不動産担保や第三者保証人の確保に苦労することなく借り入れが可能です。
手続きも非常にシンプルで、必要書類は借入申込書と本人確認書類程度で済みます。
銀行融資で求められるような詳細な事業計画書や財務諸表、税務申告書などの準備が不要なため、事務負担も大幅に削減できます。
【デメリット1】貸付限度額が積立額に依存する
小規模企業共済の貸付制度における最大のデメリットは、借入可能額が積立額に制約される点です。
一般的に掛金の7割から9割程度が上限となるため、大規模な設備投資や事業拡大には対応できない場合があります。
➡︎貸付限度額:約600万円(7割程度)になります
※もし、創業資金や大型設備投資で必要資金が1,000万円の場合、400万円不足です。
また、積立期間が短い場合は貸付限度額も低くなるため、加入したばかりの事業者にとっては実用性が限定的です。資金需要の規模と積立状況を慎重に検討し、他の資金調達手段との組み合わせを検討する必要があります。
【デメリット2】他の資金調達機会を逃すリスク
小規模企業共済の貸付を利用することで、より有利な資金調達機会を逃してしまうリスクがあります。
例えば、日本政策金融公庫の創業融資や自治体の制度融資など、より大きな金額を低金利で借りられる制度が利用できなくなる可能性があります。
特に創業間もない時期や事業拡大局面では、政府系金融機関の支援制度が充実しており、これらを活用した方が長期的な事業発展につながる場合があります。共済の貸付を先に利用してしまうと、借入枠の制約で他の制度が使えなくなることも考えられます。
また、民間金融機関との取引実績を積む機会も失われるため、将来的な資金調達の選択肢が狭まる可能性もあります。短期的な利便性だけでなく、中長期的な資金戦略を考慮した判断が重要です。
【デメリット3】将来の共済金受給額への影響
小規模企業共済の貸付を利用すると、将来受け取る共済金から元利金が差し引かれるため、老後資金や退職金としての機能が減少してしまいます。
特に長期間にわたって貸付を利用し続けた場合、本来の目的である将来保障が大幅に目減りする可能性があります。
また、共済金の受給方法(一括受取・分割受取)によっても税制上の取り扱いが変わるため、貸付利用が税務面に与える影響も考慮しなければなりません。総合的な資産形成戦略の中で、貸付制度の位置づけを明確にすることが重要です。
効果的な貸付制度の活用戦略
借入金を投資することで節税&資産運用
小規模企業共済の貸付制度を活用した高度な戦略として、借入金を投資に回すことで節税効果と資産形成を同時に実現する方法があります。
一般貸付(年1.5%)の低金利で借り入れた資金を、より高い利回りが期待できる投資商品に振り向けることで、金利差による収益を獲得できます。
例えば、利回り6.5%の投資信託などの資産運用をした場合、5%[=6.5%(投資信託のリターン)−1.5%(利息)]の利益を得ることができます。
325,000円(=500万円×6.5%)−75,000円(=500万円×1.5%)=+250,000円
➡︎この例では、借入したお金で資産運用した場合に1年間で25万円得することが可能になります!
また、事業に必要な設備投資を前倒しで実行し、即時償却制度を活用することで大幅な節税効果も期待できます。
ただし、投資による損失の可能性があるリスクも伴いますので注意しましょう。
投資戦略を実行する際は、事業計画との整合性を保ち、適切なリスク管理を行うことが成功の鍵となります。
まとめ
小規模企業共済の貸付制度を賢く運用するために
小規模企業共済の貸付制度は、適切に活用すれば事業運営の強力な武器となります。
しかし、メリットだけに注目して安易に利用すると、将来的に大きな損失を招く可能性もあります。
本記事で解説した内容を踏まえ、以下の重要ポイントを必ず押さえておきましょう。
小規模企業共済貸付制度の重要ポイント
- 年0.9%~1.5%の低金利で迅速な資金調達が可能
- 担保・保証人不要で手続きが簡単だが、貸付限度額は積立額に依存
- 一般貸付と特別貸付の制度があり、資金用途に応じた最適な選択が重要
- 他の有利な資金調達機会を逃すリスクがある
- 将来の共済金受給額が減少するデメリットを考慮する必要がある
- 借入金を投資に活用することで節税効果と資産形成を同時実現できる
成功の鍵は、短期的な利便性だけでなく中長期的な事業戦略を見据えた判断にあります。
自社の事業計画や財務状況を客観的に分析し、必要に応じて税理士や金融の専門家に相談することをお勧めします。
小規模企業共済の貸付制度を賢く運用することで、事業の成長と将来の安定を両立させる資金戦略を構築していきましょう。
小規模企業共済の基本的な仕組みから実際の貸付制度の手続き方法まで、以下の記事で詳しく解説していますので、併せてお読みください。
さらに節税効果を高めるために
小規模企業共済の貸付制度を活用した節税戦略に加えて、日常的な経費管理も重要な節税要素です。
以下の記事では、経費として計上できる項目や具体的な節税効果について詳しく解説していますので、総合的な節税戦略の構築にお役立てください。