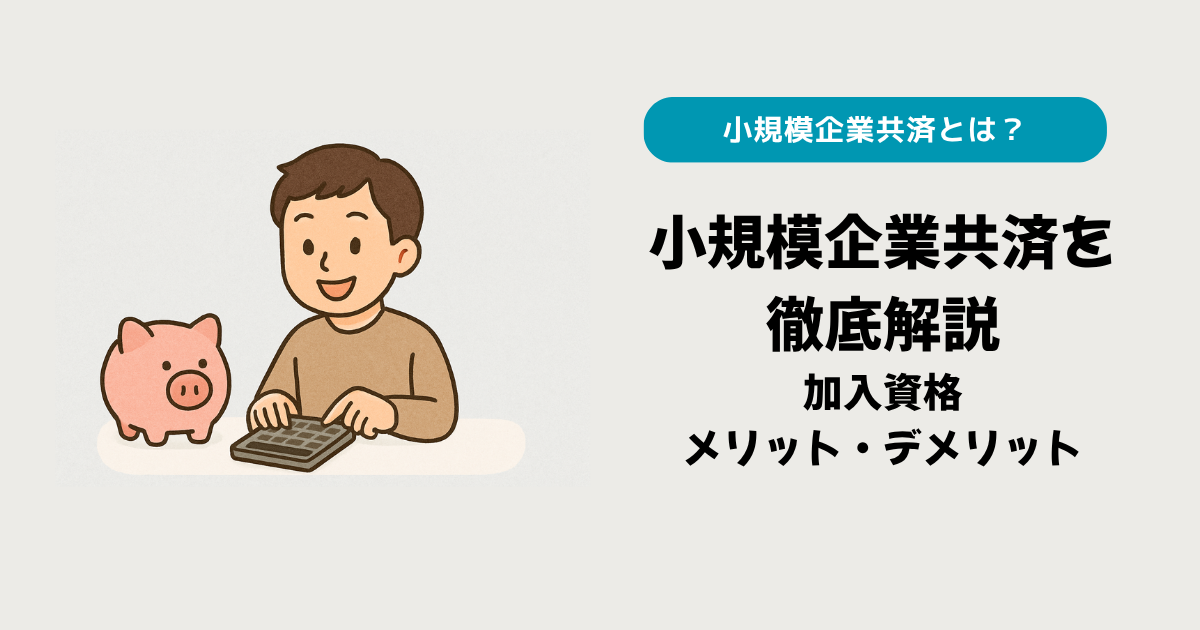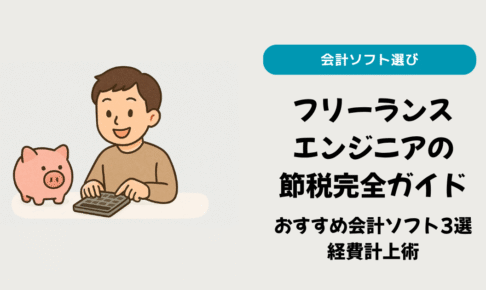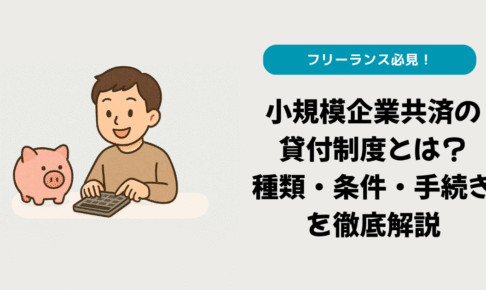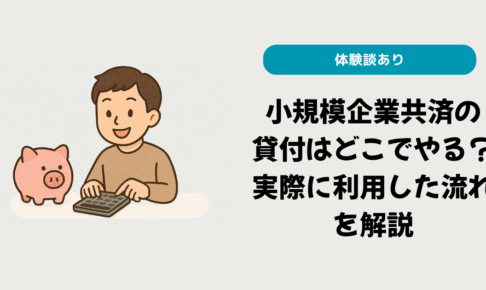- 小規模企業共済って、フリーランスでも加入できるの?
- 個人事業主の節税対策として、どんな制度なのか知りたい
- 加入条件や手続き方法が複雑で、どこから始めればいいかわからない
このような疑問や悩みを抱えていませんか?
個人事業主やフリーランスの方にとって、小規模企業共済は非常に有用な制度です。
しかし、加入条件や手続き方法が複雑で、初めての方にはハードルが高いと感じるかもしれません。
この記事では、フリーランスエンジニアの実体験を基に、小規模企業共済の加入資格について詳しく解説します。
中小企業基盤整備機構(中小機構)の公式情報を参考に、正確で実用的な情報をお届けします。
この記事を読むことで、以下のことがわかります。
- 個人事業主が小規模企業共済に加入できる条件
- 従業員数の制限や業種による違い
- 掛金の全額所得控除による節税効果
- 低金利の貸付制度の活用方法
- 加入手続きの流れ
- よくある質問への回答
小規模企業共済は、適切に活用すれば節税と資産形成を両立できる制度です。
この記事で、あなたの事業に最適な活用方法を見つけてください。
小規模企業共済とは?
小規模企業共済の定義と特徴
小規模企業共済は、中小企業の経営者や個人事業主を対象とした公的な退職金制度です。
毎月の掛金を積み立てることで、事業廃止時に退職金として受け取ることができます。
最大の特徴は、掛金の全額が所得控除の対象になることです。
つまり、所得税や住民税の計算時に掛金分を収入から差し引くことができます。
また、積み立てた掛金の範囲内で低金利の貸付を受けられる制度もあります。
運営主体と制度の概要
小規模企業共済は、中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営しています。
中小機構は、国の機関(国の中小企業政策の中核的な実施機関)として中小企業のサポートをしています。
加入者数は約159万人(2022年3月時点)と、多くの事業者に利用されています。
- 【加入者数】約159万人(2022年3月時点)
- 【掛金】月額1,000円〜70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選択可能
- 【掛金の増額・減額】月額1,000円〜70,000円までの範囲内(500円単位)で変更可能
- 【納付方法】月払い、半年払い、年払い
- 【払込方法】口座振替
個人事業主にとっての重要性
個人事業主にとって、小規模企業共済は公的な退職金制度として活用できる制度です。
会社員には厚生年金や企業年金がありますが、個人事業主にはそのような制度がありません。
小規模企業共済に加入することで、将来的に退職・廃業した時に受け取れる退職金を確保できます。
さらに、掛金の所得控除により、毎年の税金を節約できるメリットがあります。
事業資金が必要になった際は、低金利で貸付を受けられるのも大きな魅力です。
小規模企業共済の加入資格
加入条件
小規模企業共済の加入対象は、個人事業主と法人(中小企業の)の役員です。
ただし、すべての個人事業主が加入できるわけではありません。
加入には従業員数の制限があります。
業種によって、従業員数が20人以下または5人以下の条件が設けられています。
また、事業を実際に営んでいることが条件となります。
税務署への開業届や確定申告書の提出実績が必要です。
詳しくは、共済サポート naviをご確認ください。
確定申告の負担を大幅に軽減するためには、フリーランスエンジニア向け会計ソフトの導入が必須です。適切な経費計上と併せて活用しましょう。
従業員数の制限について
従業員数の制限は、業種によって異なります。
| 業種 | 従業員数 |
|---|---|
| 建設業・製造業・運輸業・不動産業・農業・サービス業(宿泊業、娯楽業に限る)等 | 20人以下 |
| 商業(卸売業・小売業)・サービス業(宿泊業、娯楽業を除く) | 5人以下 |
ここで言う従業員数とは、正社員として雇用されている方を指し、パートやアルバイト、家族従業員は従業員数に含まれません。
従業員数の制限は、共済加入時点での判断になるため、一度加入すれば継続加入が可能です。
その後、事業規模が大きくなっても加入資格は失われません。
小規模企業共済のメリット・デメリット
メリット
全額所得控除による節税効果
小規模企業共済の最大のメリットは、掛金の全額が所得控除になることです。
毎月の掛金を積み立てることで、所得税と住民税を大幅に節約できます。
例えば、月額3万円の掛金を積み立てた場合、年間36万円が所得控除されます。
課税所得400万円の場合、年間約11万円の節税効果が期待できます。
- 課税所得:400万円
- 掛金:毎月3万円
- 積立額:年間36万円
➡︎所得税・住民税が年間109,500円安くなります
この掛金(月3万円)による積立額(年間36万円)は、将来退職金として受け取れるお金です。
要するに、年間36万円預けてるだけで、約10万円ほど税金が安くなるということになります。
これは、銀行預金では絶対に得られない効果と言えます。
仮に、年間36万円を銀行に預けた場合でも、360,000円×0.001%(銀行普通預金の金利)=利息3.6円くらいの利益です。
小規模企業共済は、掛金を積み立てながら、同時に税金も節約できる一石二鳥の制度と言えるでしょう。
低金利の貸付制度
小規模企業共済には、低金利の貸付制度があります。
一般貸付は年1.5%、特別貸付は年0.9%という低金利です。
銀行の個人事業主向けローンと比べて、圧倒的に有利な条件です。
積み立てた掛金の範囲内で、理由を問わずに借りることができます。
保証人や担保が不要で、手続きも簡単に済みます。
小規模企業共済の貸付制度については、別記事で詳しく解説しています。
掛金の柔軟な変更
小規模企業共済の掛金は、いつでも変更可能です。
月額1,000円〜70,000円まで、500円単位で自由に設定できます。
事業の収益状況に応じて、掛金を増額・減額できます。
例えば、資金繰りが厳しい時は最低額の1,000円まで下げることも可能です。
そして、変更手続きも簡単で、書類またはオンラインで手続きできます。
事業の成長に合わせて、柔軟に積み立て額を調整できるのが魅力です。
退職金制度としての活用
小規模企業共済は、個人事業主の退職金制度として活用できます。
会社員には厚生年金や企業年金がありますが、個人事業主にはありません。
小規模企業共済に加入することで、将来の退職金を確保できます。
事業廃止時には、積み立てた掛金を退職金として受け取れます。
解約ではなく退職金として受け取ることで、元本割れを回避できます。
長期的な資産形成と老後の資金準備を同時に実現できます。
デメリット
20年未満の解約時の元本割れ
小規模企業共済の最大のデメリットは、20年未満で解約すると元本割れすることです。
掛金を積み立てても、短期間で解約すると掛けた金額より少なく返ってきます。
これは、手数料や運用コストが差し引かれるためです。
例えば、月額1万円を5年間積み立てた場合、60万円を掛けても約50万円しか戻りません。
ただし、20年以上継続すれば、元本を上回る金額を受け取れます。
解約を避けるため、長期的な視点での加入を検討する必要があります。
資金の流動性の制限
小規模企業共済の掛金は、原則として解約まで引き出せません。
急な資金が必要になった場合でも、掛金を一時的に停止することはできません。
ただし、貸付制度を利用することで資金調達は可能です。
積み立てた掛金の範囲内で、低金利で借りることができます。
しかし、貸付制度も利用できないという場合には、資金の流動性が制限されることになります。
事業の資金繰りを考慮して、適切な掛金設定が重要です。
掛金の継続義務
小規模企業共済は、掛金の継続納付が義務となっています。
一度加入すると、解約するまで掛金の納付を継続する必要があります。
ただし、掛金の減額は可能です。
事業の収益が悪化した場合は、月額の最低額1,000円まで下げることで、継続加入を維持できます。
解約を避けつつ、事業の状況に合わせて掛金を調整する柔軟性があります。
低金利の貸付制度を利用できる
小規模企業共済の一つの特徴として、貸付制度があります。
自分で積立した額の7〜9割を借りることができます。
返済期限は1年です。(借入金額により、期間の変更可能です)
しかし、お金を借りるということなので、返済と利息の支払いが必要になります。
利息は年1.5%です。
ただ、返済期限の1年後に利息分さえ支払いをすれば、そのまま継続で借りることができます。
加入手続きの流れ
加入手続きの方法
小規模企業共済の加入手続きには「窓口での手続き」「オンラインでの手続き」の2つの方法があります。
窓口での手続きは、委託機関や金融機関の本支店で行えます。
商工組合中央金庫(商工中金)や地方銀行などの指定金融機関でも手続き可能です。
必要書類を揃えていきましたが、窓口が少し混雑していたため、手続き完了まで大体1時間程度かかりました。
オンラインでの手続きは、共済制度オンラインから行えます。
インターネット環境があれば、自宅やオフィスから手続きが可能です。
提出書類のアップロードが必要になりますので、用意するようにしましょう。
もし、加入手続きに不安を感じるは窓口での手続きをお勧めです。
不明な点を直接質問できるメリットがあります。
よくある質問と回答
Q1: フリーランスでも加入できますか?
A: はい、フリーランスでも加入できます。
フリーランスは個人事業主として扱われるため、加入資格があります。
ただし、事業を実際に営んでいることが条件となります。
副業や趣味の範囲ではなく、収益を目的とした事業活動である必要があります。
税務署への開業届の提出や、確定申告書の提出実績が必要です。
従業員数が業種の制限内であれば、問題なく加入できます。
フリーランスエンジニアやデザイナーなど、多くの方が加入しています。
Q2: 従業員を雇ったら加入資格は失われますか?
A: 一度加入すれば、継続加入が可能です。
従業員を雇って事業規模が大きくなっても、加入資格は失われません。
安心して事業拡大を検討できるのが大きなメリットです。
ただし、新規加入時には従業員数の制限があります。
製造業などは20人以下、商業・サービス業などは5人以下が条件です。
Q3: 掛金はいつでも変更できますか?
A: はい、いつでも変更可能です。
掛金は月額1,000円〜70,000円の間で、500円単位で変更できます。
変更手続きは郵送やオンラインで簡単に済みます。
事業の収益状況に応じて、掛金の増額・減額を自由に行えます。
ただし、最低額の1,000円は継続納付する必要があります。
資金繰りが厳しい時は最低額まで下げることも検討しましょう。
Q4: 解約時の返戻金はどうなりますか?
A: 加入期間によって返戻金が変わります。
20年未満で解約すると、元本割れになります。
手数料や運用コストが差し引かれるためです。
20年以上継続すれば、元本を上回る金額を受け取れます。
解約を避け、長期的な視点での加入を検討することをお勧めします。
事業廃止時は退職金として受け取れます。
貸付制度を利用した場合
貸付制度を利用して事業を廃止した場合、自分が受け取る積立金から貸付利用分の金額が引かれて戻ってきます。
例えば、事業廃止した時の退職金が1000万円、貸付制度で借りた額が500万円の場合、1000万円−500万円=500万円が戻ってくるということになります。
貸付制度で既に受け取った分が相殺されて、その残りを退職金として受け取ることになります。
まとめ
小規模企業共済の加入資格と活用方法
小規模企業共済は、個人事業主にとって非常に有用な制度です。
この記事では、加入資格から実際の手続きまで詳しく解説しました。
特に重要なポイントは以下の通りです。
加入資格のポイント
- 個人事業主と法人の役員が加入対象
- 従業員数の制限(製造業20人以下、商業・サービス業5人以下)
- 事業を実際に営んでいることが条件
- 開業届や確定申告書類などの提出が必要
メリットのポイント
- 掛金の全額が所得控除で大幅な節税効果
- 低金利の貸付制度(一般貸付年1.5%、特別貸付年0.9%)
- 掛金の柔軟な変更が可能(月額1,000円〜70,000円)
- 個人事業主の退職金制度として活用可能
デメリットのポイント
- 20年未満の解約時は元本割れのリスク
- 資金の流動性が制限される
- 掛金の継続納付が義務
実践的なアドバイス
- 事業開始後すぐに加入を検討する
- 無理のない掛金設定から始める
- 長期的な視点で加入を検討する
- 事業の資金繰りを優先して判断する
小規模企業共済は、適切に活用すれば節税と資産形成を両立できる制度です。
ただし、長期的な視点での加入が重要になります。
事業の状況に応じて柔軟に対応できる制度なので、個人事業主の方は積極的に検討することをお勧めします。