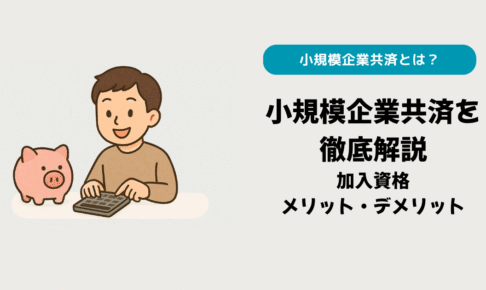- フリーランスと会社員、どちらが収入面で有利なんだろう?
- 会社員の安定性は魅力的だけど、フリーランスの高収入も気になる。
- 実際の手取り額はどれくらい違うのか、将来の収入はどうなるのか。
エンジニアとして働いているあなたは、こんな疑問を抱えていませんか?
この記事では、2025年の最新データに基づいて、フリーランスエンジニアと会社員エンジニアの年収を徹底比較します。
業界平均データや実際の事例を交えながら、税金や経費を考慮した実質的な収入差を紹介しています。
年齢別・スキル別の収入推移、将来性、リスク要因まで詳しく解説します。
この記事を読むことで、あなたの状況に最適な選択肢が明確になります。
具体的な数値と事例で、収入面での判断基準を解説しています。
Contents
フリーランスエンジニアvs会社員エンジニア 年収徹底比較
平均年収の比較(2025年最新データ)
フリーランスエンジニアと会社員エンジニアの年収差は、多くの人が気になるポイントです。
2025年の最新データによると、会社員エンジニアの平均年収は約450万円から650万円となっています。
一方、フリーランスエンジニアの平均年収は600万円から800万円程度です。
この差は、働き方の自由度とリスクの違いを反映しています。
会社員は安定性を重視した給与体系です。
フリーランスは成果に応じた単価制が基本であり
ただし、フリーランスは経費や税金の負担が重いため、手取り額では差が縮まることが多いです。
業界やスキルによっても収入差は大きく変わります。
Web系やAI分野のエンジニアは高単価案件が多く、フリーランスでも年収1000万円を超えるケースがあります。一方、SIer系のエンジニアは会社員の方が安定した収入を得やすい傾向があります。
年齢別・経験年数別の収入推移
収入の変化の違い
会社員エンジニアの場合、年功序列の影響で、経験年数に応じて着実に収入が増加することが一般的です。
20代後半で400万円程度から始まり、30代で500万円、40代で600万円台に到達するのが多いでしょう。
フリーランスエンジニアは、スキルと営業力次第で収入が大きく変動します。
20代後半のフリーランスは300万円から500万円程度ですが、30代になると600万円から800万円、40代では800万円から1200万円と幅広い収入分布になります。
経験年数による収入の伸び率
会社員は年齢に応じた安定した昇給が見込める傾向があります。
フリーランスは自己努力次第で収入を大幅に増やせる可能性がありますが、継続的なスキルアップと営業活動が不可欠です。
スキルレベル別の収入差
スキルレベルの収入差
スキルレベルによる収入差は、フリーランスの方が顕著に現れます。
初心者レベルのフリーランスエンジニアは年収300万円から400万円程度ですが、中級者になると500万円から700万円、上級者では800万円から1500万円と大きな差が生まれます。
会社員エンジニアの場合、スキルレベルよりも年齢や役職が収入に影響します。
同じスキルレベルでも、大企業と中小企業では年収に100万円以上の差があることも珍しくありません。
また、管理職への昇進により収入が大幅に増加するケースもあります。
手取り額の真実|税金・経費を考慮した実質収入
会社員エンジニアの手取り額計算例
例:会社員エンジニア(年収600万円)
会社員エンジニアの年収600万円の場合を例に、実際の手取り額を計算してみます。
給与から控除される項目は、所得税、住民税、社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険)です。
これらの控除額は約120万円程度となり、手取り額は480万円程度になります。
そのほかに、通勤手当や住宅手当などの各種手当も、実質的な収入として考えることができます。
また、福利厚生の経済的価値も知っておくと良いでしょう。
社会保険料は労使折半(会社と社員自身で半分ずつ負担する仕組み)です。健康保険料・厚生年金、各種保険の加入費用などを会社が負担してくれることで、年間50万円から100万円の経済的メリットも受けていると言えます。
フリーランスエンジニアの手取り額計算例
例:フリーランスエンジニア(年収800万円)
フリーランスエンジニアの年収800万円の場合を例に、経費と税金を差し引いた手取り額を計算します。
主な経費として、事務所費・通信費・交通費・書籍代・セミナー参加費など年間100万円程度が必要でしょう。
また、国民健康保険料・国民年金保険料・所得税・住民税で約180万円程度かかります。
以上の例の場合、手取り額は520万円程度になります。
所得税と住民税の計算では、合計収入から経費を差し引いた所得に対して税金が計算されます。
実際の税負担は会社員よりも軽くなる場合があります。ただし、確定申告のための会計ソフトや税理士費用も必要になることを考慮に入れましょう。
収入の変動リスクも、手取り額に影響を与える重要な要素です。
案件が途切れた場合の収入減少や、病気や怪我で働けない期間の収入損失は、実質的な手取り額を大きく下げる要因になります。
また、老後の年金額も会社員よりも待遇が少ないため、老後資金などの準備を早いうちから対策することが重要です。
業務委託契約のメリットを活用することで、税負担を軽減できる場合があります。
福利厚生の経済的価値を考慮した比較
会社員の福利厚生
会社員の福利厚生は、実質的な収入として大きな価値を持ちます。
健康保険の家族扶養制度、厚生年金の老後保障、雇用保険の失業給付などは、個人で加入する場合と比較して年間100万円以上の経済的メリットがあります。また、退職金制度も老後のための重要な収入源になります。
会社員の安定性は大きな安心感を与えてくれます。
特に家族がいる場合や、老後の生活を重視する場合は、会社員の働き方は向いているでしょう。
フリーランスの対策
フリーランスは、すべての保障を自己負担で準備する必要があります。
失業時の保障は無く、退職後の生活資金も自己責任で準備しなければなりません。
生命保険・医療保険・年金保険など、備えのための保険には追加費用がかかります。
一方、フリーランスは若いうちから高収入を得て、自己投資や資産形成に回す戦略が有効的です。
節税対策・退職金制度としても利用できる小規模企業共済は、フリーランスにとって非常に活用できる制度です。
収入の安定性とリスク比較
会社員エンジニアの収入安定性
会社員エンジニアの最大のメリットは、毎月安定した給与が保証されることです。
基本給に加えて、残業手当や各種手当なども確実に支給されます。ボーナスも年2回の定期支給が一般的で、年間収入の予測が立てやすくなっています。
会社が倒産するリスクはありますが、大企業であれば比較的安全でしょう。
また、有給休暇や社会保険の適用により、病気やケガで働けない期間も収入が保障されます。
さらに、退職金制度も整っているため、長期的な収入安定性は高いと言えるでしょう。
フリーランスエンジニアの収入変動要因
フリーランスエンジニアの収入は、案件の獲得状況によって大きく変動します。
高単価案件や繁忙期には高収入が期待できますが、案件が少ない時期は収入が激減する可能性があります。クライアントの業績悪化や予算削減により、突然の案件終了も起こり得ます。
技術トレンドの変化も収入に影響したりします。
需要の高い技術スキルを持っていれば高単価で案件を獲得できる傾向ですが、古い技術しか扱えない場合は案件数が減少する傾向もあります。
また、経済状況や季節による案件数の変動も無視できません。
社会情勢による影響もあります。
複数エージェントを活用することで、収入の安定性を大幅に向上させることができます。
失業リスクと対策方法
会社員エンジニアの失業リスクは、会社の業績やリストラによって左右されます。
しかし、雇用保険により一定期間の収入保障があります。転職活動中も健康保険が継続されるため、医療費の負担も軽減されます。
フリーランスエンジニアは、案件終了と同時に収入が途絶えるリスクがあります。
次の案件を獲得するためのエージェントとの関係づくりや複数クライアントとの契約などで、リスク分散を図ることが重要です。
また、緊急時の資金用に、最低6ヶ月分の生活費を貯蓄しておくことをお勧めします。
技術スキルの継続的な向上も、失業リスクを軽減する効果的な対策です。
新しい技術を学び、ポートフォリオを充実させることで、案件獲得の可能性を高めることができます。
将来性とキャリアアップの可能性
技術トレンドへの対応力比較
フリーランスエンジニアの学習戦略
フリーランスエンジニアは、市場の需要に合わせて技術を選択する必要があります。
現在、AI・機械学習(Python、TensorFlow)、クラウド技術(AWS、Azure)、セキュリティ(認証・暗号化)が高単価案件の中心です。
学習コストは年間50万円から100万円(書籍・セミナー・オンライン講座)が一般的で、月20時間程度の学習時間が必要です。
自己学習の効果は、実案件での即戦力として評価されます。
UdemyやCourseraなどのオンライン講座を活用し、GitHubでポートフォリオを公開することで、技術力をアピールできます。
ただし、体系的な学習が難しいため、基礎知識の穴が生じるリスクがあります。
会社員エンジニアの学習環境
会社員エンジニアは、企業の技術戦略に沿った学習が求められます。
大手企業では年間100万円以上の研修予算があり、AWS認定やAzure認定などの資格取得費用を全額負担してくれる場合が多いです。
社内技術勉強会やハッカソンへの参加も、業務時間内で可能です。
企業研修の効果は、体系的な知識習得にあります。
先輩エンジニアからの指導や、社内の技術ドキュメントを活用できるため、基礎から応用まで効率的に学習できます。
ただし、最新技術の導入が遅れる場合があり、市場トレンドとの乖離が生じる可能性があります。
学習投資対効果の比較
フリーランスの場合、学習投資が直接収入に反映されます。
AI・機械学習スキルを習得すれば、単価が月10万円から15万円アップするケースが一般的です。
会社員の場合、昇進や転職での収入向上につながります。
クラウド技術の資格取得により、年収50万円から100万円の増加が期待できます。
キャリアパスと成長機会
フリーランスエンジニア
フリーランスエンジニアのキャリアパスは、技術スペシャリストとしての道が一般的です。
特定分野の専門性を高めることで、高単価案件を獲得できます。
また、複数の業界やプロジェクトに関わることで、幅広い知識と経験を積みフルスタックエンジニアとしての道も可能です。
フリーランスエンジニアの収入向上には、技術力と営業力に大きく依存します。
需要の高い技術を習得し、実績を積み重ねることで、年収1000万円以上も十分に可能です。
ただし、継続的な学習と自己投資が不可欠になります。
会社員エンジニア
会社員エンジニアは、技術職から管理職への転身が可能です。
プロジェクトマネージャーや技術責任者として、チームを率いる立場に昇進できます。
また、社内での異動により、様々な部署での経験を積むことも可能です。
会社員エンジニアの収入向上は、昇進と年功序列に基づきます。
管理職への昇進により大幅な収入増加が期待できます。
また、大企業では退職金制度により、長期的な収入保障も得られます。
業界別・職種別の収入事情
Web系・SIer・スタートアップでの違い
Web系
Web系企業は、技術力重視の文化が強く、若手でも高収入を狙える環境です。
特に、フリーランスエンジニアにとっては、案件単価が高く、技術的な裁量も大きいため人気があります。
ただし、技術の移り変わりが激しく、継続的な学習が求められます。
SIer
SIerは、大規模プロジェクトが多く、安定した収入が期待できます。
会社員として働く場合、年功序列による昇給が一般的で、長期的なキャリア形成がしやすい環境です。
しかし、技術的な自由度は比較的低い傾向があります。
SESとフリーランスの違いを理解することで、より適切な選択が可能になります。
スタートアップ
スタートアップ企業は、リスクとリターンが大きい環境です。
企業の事業が成功すれば大幅な収入増加やストックオプション(自社株購入の権利)の恩恵を受けられます。
ただし、会社の存続リスクも高く、労働時間も長くなる傾向があります。
フロントエンド・バックエンド・インフラ別の収入
フロントエンドエンジニア
フロントエンドエンジニアは、需要が高く、案件も豊富にあります。
特に、ReactやVue.jsなどの最新フレームワークに精通していると、高単価案件を獲得しやすくなります。
ただし、技術の移り変わりが激しいため、最新技術のキャッチアップや継続的な学習が必要です。
バックエンドエンジニア
バックエンドエンジニアは、システムの根幹を担う重要な役割です。
JavaやPythonなどの言語に加えて、データベース設計やAPI設計のスキルも求められます。
経験年数に応じて収入が大きく伸びる傾向があります。
インフラエンジニア
インフラエンジニアは、クラウド技術の普及により需要が高まっています。
AWSやAzureなどのクラウドプラットフォームに精通していると、特に高収入が期待できます。
また、セキュリティ知識も重要で、専門性の高い分野になります。
実際の収入事例と体験談
以下の事例は、業界の平均データや一般的な収入水準を参考にした参考事例です。
実際の収入は、個人のスキル、経験、勤務先、地域などにより大きく異なります。
年収450万円の会社員エンジニア事例(Aさん・28歳・SIer)
Aさんは中規模SIerで働く会社員エンジニアです。
月給32万円、残業手当月5万円、ボーナス年2回(各60万円)で年収450万円です。
手取り額は月28万円(所得税・住民税・社会保険料控除後)になります。
経費は通勤費月2万円のみで、技術研修費用は会社負担です。
JavaとSpring Bootの資格取得支援も受けられ、年間50万円の学習投資を無償で行えます。
有給休暇は年間20日取得し、病気時も安心して休めます。
成功要因は、体系的な技術習得にあります。
先輩からの指導により、基礎から応用まで効率的に学習できました。
プロジェクトマネージャーへの昇進も視野に入れており、年収600万円台への向上が期待できます。
年収680万円のフリーランスエンジニア事例(Bさん・32歳・Web系)
BさんはWeb系フリーランスエンジニアとして活動しています。
月間案件収入は55万円(React・Node.js案件)で、年収680万円です。
経費は事務所費月3万円、通信費月1万円、書籍代月2万円、セミナー参加費月3万円の合計月9万円です。
税金は国民健康保険料月2万円、国民年金月1.5万円、所得税・住民税月8万円で、手取り額は月34.5万円になります。
複数クライアント(3社)と契約し、リスク分散を図っています。
成功要因は、需要の高い技術の習得と営業力の向上です。
ReactやNode.jsの最新技術を積極的に学び、GitHubでポートフォリオを公開しています。
案件の質を重視し、単価の低い案件は断ることで、収入の質を向上させました。
年収1200万円の成功事例(Cさん・38歳・AI専門)
Cさんは大手IT企業のAI技術責任者として働いています。
基本給月60万円、役職手当月10万円、ボーナス年2回(各200万円)で年収1200万円です。
手取り額は月55万円で、退職金制度も充実しています。
技術的な判断に加えて、部下10名の育成とプロジェクト管理を担当します。
AI・機械学習の専門知識とマネジメント能力の両方が求められる立場です。
成功要因は、専門分野での深い知識とリーダーシップです。
AI・機械学習の最新技術を継続的に学習し、チーム全体の技術レベル向上に貢献しています。
技術力だけでなく、人材育成能力も評価され、管理職への昇進につながりました。
年収1100万円のフリーランス成功事例(Dさん・35歳・AI専門)
DさんはAI・機械学習専門のフリーランスエンジニアです。
月間案件収入は90万円(Python・TensorFlow案件)で、年収1100万円です。
経費は年間120万円(高額なGPUサーバー代含む)で、手取り額は月65万円になります。
複数のスタートアップと契約し、AIモデルの開発から運用まで一貫して担当します。
技術力に加えて、営業力とコミュニケーション能力も重要です。
成功要因は、希少性の高い技術スキルと継続的な学習投資です。
AI・機械学習の専門知識を深め、実績を積み重ねることで高単価案件を獲得しています。
月30時間の学習時間を確保し、常に最新技術をキャッチアップしています。
いずれの場合も、技術力の向上とキャリア戦略の重要性が共通しています。
自分の強みを活かし、市場の需要に合わせてスキルを磨き続けることが、収入向上につながります。
どちらを選ぶべき?判断基準と選択のポイント
年齢・家族構成を考慮した選択基準
20代前半のエンジニアは、技術力を磨くことを優先すべきです。会社員として基礎を固め、幅広い経験を積むことが将来の選択肢を広げます。安定した収入で技術研修に投資し、スキルアップを図ることが重要です。
30代で結婚や子育てをしている場合は、安定性を重視することをお勧めします。会社員の社会保険や有給休暇は、家族の安心につながります。ただし、技術力に自信があり、副業から始めることも検討できます。
40代以降は、経験を活かした専門性の高いフリーランスが有利です。ただし、急な転身はリスクが大きいため、段階的な移行を検討しましょう。家族の理解と十分な資金準備が不可欠です。
スキルレベルに応じた推奨選択
未経験から3年目程度のエンジニアは、会社員として働くことをお勧めします。
先輩からの指導や体系的な研修により、効率的にスキルアップできます。
また、チーム開発の経験も貴重です。
5年以上の経験があるエンジニアは、自分の強みを活かした選択が可能です。
特定分野の専門性が高い場合は、フリーランスとして高単価案件を狙えます。
ただし、営業力や自己管理能力も必要です。
10年以上のベテランエンジニアは、技術力と経験を武器にした選択肢が広がります。管理職としてのキャリアを目指すか、技術スペシャリストとして独立するか、自分の価値観で決めることが重要です。
移行を検討する際のチェックリスト
フリーランスへの移行を検討する際は、まず現在のスキルレベルを客観的に評価しましょう。特に、需要の高い技術を習得しているか、実績を証明できるポートフォリオがあるかを確認してください。
資金面では、最低6ヶ月分の生活費を確保しておくことは、いざという時の備えになります。
また、社会保険や税金の知識も必要になります。
複数のクライアントとの関係構築や、案件獲得の営業力も事前に準備しましょう。
会社員への転職を検討する場合は、現在の技術スキルが企業で求められているかを確認してください。履歴書や職務経歴書の準備、面接対策も重要です。
また、給与や福利厚生の条件も十分に比較検討しましょう。
まとめ
フリーランスエンジニアと会社員エンジニアの年収比較について詳しく解説しました。
どちらを選ぶかは、あなたの年齢、スキルレベル、ライフスタイルによって決まります。
重要なポイント
- 平均年収:フリーランス600-800万円 vs 会社員450-650万円
- 手取り額:経費や税金を考慮すると差が縮まる傾向
- 収入安定性:会社員が圧倒的に安定、フリーランスは変動大
- 学習投資:フリーランスは自己負担、会社員は企業支援
- キャリアパス:会社員は管理職、フリーランスは技術スペシャリスト
- 将来性:両方とも技術力向上で収入アップ可能
年齢別の推奨選択
20代は会社員で基礎を固め、30代以降はスキルに応じて選択を。
フリーランスへの移行は、最低6ヶ月分の生活費と技術力の準備が必要です。
成功の鍵
技術トレンドへの対応力と継続的な学習が収入向上の決め手です。
AI・クラウド・セキュリティ分野のスキル習得で、どちらでも高収入が期待できます。
あなたの状況に合わせて、慎重に選択してください。
どちらを選んでも、技術力の向上とキャリア戦略が成功への道筋となります。